歯学部は留年が多い!留年する人の特徴・理由を徹底解説!
- 公開日:2024.01.11
- 更新日:2024.01.11
- 331 views
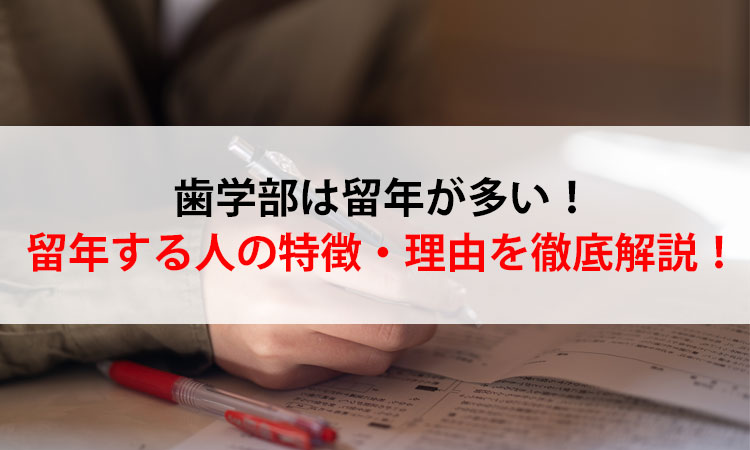
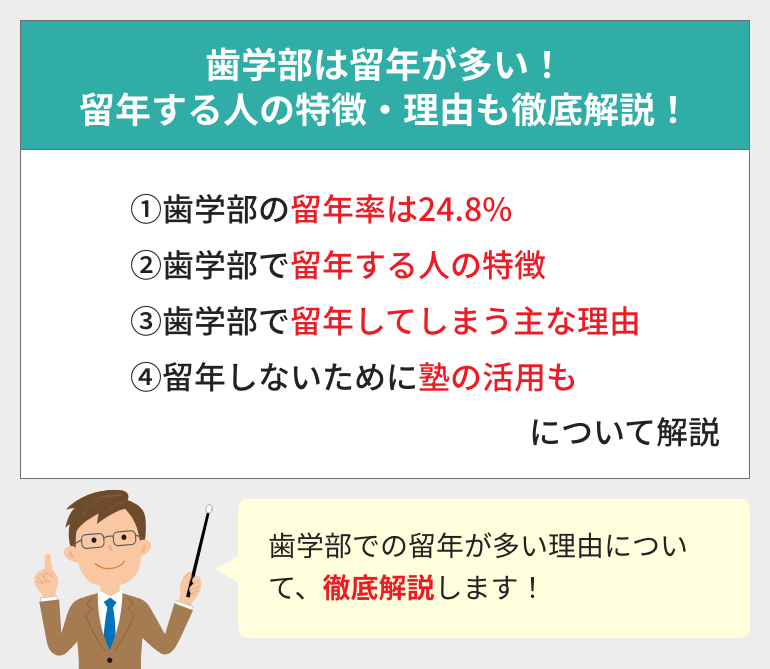
あなたは、
- 歯学部で留年する人の特徴を知りたい
- 歯学部で留年してしまう主な理由を知りたい
- 歯学部で留年しないための対策を知りたい
とお考えではありませんか。
結論、歯学部の留年は非常に多いです。
なぜなら、
- 習う項目が膨大で、深い理解を求められる内容も多い
- 卒業試験は国家試験に合格する見込みのある学生しか突破できないようなっている
からです。
できるなら、効率よく勉強も学業以外の活動にも取り組み、留年しないで卒業したいですよね。
この記事では
1章で、歯学部の実際の留年率
2章で、歯学部で留年する人の特徴
3章で、歯学部で留年してしまう主な理由
4章で、留年しないためには塾の活用も有効について解説します。
この記事を読めば、留年する人の特徴や理由を知れます。
また、有効な対策法も知れます。
この記事を読んで、効率よく勉強し、留年せずに有意義な歯学部生活を過ごしましょう。
目次
1章:歯学部の留年率は24.8%
この章では、歯学部の留年率は
- 在学時に一度でも留年・休学をした6年生は6%
- 留年率は私立と国立でも違いがある
それぞれについて説明します。
1-1:在学時に一度でも留年・休学をした6年生は37.6%
令和5年度の在学時に、一度でも留年・休学をした6年生は37.6%でした。
令和5年度の歯学部の全体は24.8%で、いずれも高い留年率でした。
原因としては、
- 歯科医師過剰問題の影響で、歯科医師国家試験の合格者数が年々削減されていること
- 歯学部志願者の減少からくる歯学部志願者の質の低下していること
- 歯科医師国家試験の難化のため、合格率を保つため留年が増えていること
- 歯科医師国家の合格率が大学の評価に影響するため、国家試験に合格できそうな学生を進級・卒業させていること
があげられます。
1-2:留年率は私立と国立でも違いがある
歯学部の留年率は、私立大学が国立大学かでも違いがあります。
令和5年度の歯学部(歯学科)における留年・休学者の割合は、私立大学で28.8%、国立大学で14.7%でした。
私立大学の方が、国立大学よりも留年率が2倍以上高い傾向にありました。
私立大学は、国立大学と比較すると滑り止めとして受験する場合や、推薦入試や倍率が低いため受験した場合が多く、受験生の質の低下の影響をより受けやすいと考えられます。
また、私立大学は、国家試験合格率が減少し、大学の評価が下がれば経営自体に影響が出る可能性があり、国立大学より進級・卒業の基準を厳しくせざるを得ないと考えられます。
これらの影響から、私立大学の方が国立大学よりも留年率が高い傾向があると考えられます。
2章:歯学部で留年する人の特徴
この章では、歯学部で留年する人の特徴について解説します。
- 出席も試験もギリギリ狙い
- 成績の良い友人が少ない
- 勉強法が独自
- 進級や留年に関心が薄い
- いつも部活の練習をしている
- 試験の制度にだけやたら詳しい
それぞれ説明します。
2-1:出席も試験もギリギリ狙い
歯学部で留年する学生の中には、出席と試験の両方でギリギリを狙うタイプの人もいます。
このような学生は、大学を休みがちで、出席日数も試験の点数もギリギリで合格ラインを超えることを目指しています。
一見、時間・労力は効率的なように思えますが、実際にはハイリスクな手法です。
なぜなら、出席日数がギリギリだと、教授や教員からの評価が低くなる可能性があるからです。
さらに、試験の点数がギリギリであれば、一つのミスが致命傷となり、そのまま試験に不合格となってしまう可能性もあります。
また、このような学生は、試験についての情報を得るための友人ネットワークが乏しく、重要な情報を逃す可能性も高いです。
2-2:成績の良い友人が少ない
歯学部で留年する学生の特徴の一つに、成績の良い友人が少ないということもあげられます。
単純に友人が少ない場合、友人ネットワークを通じて学内試験やその他の重要な情報得ることができません。
友人が少ないと、ただ単に社交的な側面で問題となるだけでなく、学業においても大きな影響を受けてしまいます。
たとえば、過去問や試験に関する貴重な情報は、多くの場合、友人や先輩から得られるものです。
友人が少ない学生は、このような情報にアクセスする機会が減り、結果として試験の成績にも影響を受ける可能性が高くなります。
さらに、友人が少ない学生は、重要な試験に対する緊張感を共有する機会も少なく、緊張感が薄れることがあります。
このような状況が続くと、学業に対するモチベーションが下がり、最終的には留年につながる場合もあります。
さらに、成績の良い友人が少ないと、歯学部での勉強もより大変なものになります。
どの人とどのように過ごし、勉強密度の濃い時間を過ごせるかが非常に重要です。
成績のよい人からの情報に触れると、試験のポイントをしっかり抑えることができますし、わからない点の質問もできます。
また、成績のよい人の勉強の進み具合を知り、自分の勉強の進む具合が十分かどうかも確認できます。
成績のよい人たちと時間を過ごすことで、よい影響をたくさん受けられるので、成績のよい人と時間を過ごすことは非常にオススメです。
2-3:勉強法が独自
歯学部で留年する学生の特徴として、独自の勉強法で勉強してしまうということがあげられます。
このタイプの学生は、努力家で多くの勉強時間をとっています。
しかし、その努力が報われない場合も多いです。
独自の勉強法で勉強する学生は、効率の悪い参考書使い方をしてしまったり、難易度の高い問題集や分量の多い問題集に手を広げすぎたりします。
また、必要以上に細かい部分まで突き詰める傾向があり、その結果、大事なポイントを見失ってしまいます。
このような学生は、自分の方法が正しいと信じていることが多く、自分の勉強法に問題があると気づくことが少ないです。
その結果、試験での成績が伸び悩み、最終的には留年につながる可能性が高くなります。
結論として、独自の勉強法はリスクが大きいです。
努力だけではなく、その努力が正しい方向に向かっているかどうかを常に評価し、必要ならば戦略を練り直すことが重要です。
2-4:進級や留年に関心が薄い
歯学部で留年する学生の中には、進級や留年に対する関心が薄いという学生がいます。
このような学生は、大学生活において学業よりも、他の活動や趣味に熱中している場合が多いです。
その結果、定期試験や授業の出席、さらには国家試験に対する準備が不十分となり、留年のリスクが高まります。
2-5:いつも部活の練習をしている
歯学部で留年する学生の中には、部活動に熱心で、そのために学業がおろそかになってしまう人もいます。
このような学生は、部活動で結果を出すことや、仲間との絆を非常に大切にしています。
その結果、学業に対して時間とエネルギーを十分に割けません。
部活動自体は悪いことではなく、実際、多くの学生が部活動を通じてリーダーシップやコミュニケーション能力を高めています。
しかし、その活動が学業に対する影響を及ぼすようになると、問題が生じます。
なぜなら、部活動と学業のバランスをうまく取れないと、試験の成績が低くなったり、出席日数が足りなくなったりする可能性があるからです。
そして、最終的にはそれが留年に繋がってしまうことになります。
部活動に熱心すぎる学生は、その活動が学業に与える影響をしっかりと認識することが重要です。
必要に応じて、優先順位を見直すことも検討しましょう。
2-6:試験の制度にだけやたら詳しい
歯学部で留年する学生の中には、試験の制度にだけ非常に詳しいという学生もいます。
このような学生は、試験の形式や採点基準、さらには教授の傾向まで詳しく知っています。
一方で、実際の学習内容にはあまり手を付けていません。
試験の制度に詳しいことは、一見すると有利に思えますが、それだけでは不十分です。
制度を知っているだけでなく、その知識を活かして効率的に学習する必要があります。
このタイプの学生は、制度に詳しいことで安心感を得てしまい、その結果、実際の学習に対するモチベーションが低い場合があります。
試験の制度にだけ焦点を当てすぎると、実際に必要な知識やスキルがおろそかになります。
そして、最終的には、国家試験にも影響を与える可能性があります。
結論として、試験の制度に詳しいことは一つの強みでありますが、それだけでは不十分ということです。
実際の学習内容にもしっかりと取り組むことが、成功への鍵です。
3章: 歯学部で留年してしまう主な理由
この章では、歯学部で留年してしまう主な理由について解説します。
- 勉強の仕方が分からず、対応不十分で留年してしまう
- 専門科目が始まりテスト範囲が膨大で翻弄されて留年してしまう
- 4年次のCBTの範囲が膨大で留年してしまう
- 5年次の臨床実習で精神的にダメージを受け留年してしまう
- 臨床実習に追われ、総合試験対策が十分にできず留年してしまう
- 6年次に難化した卒業試験で留年してしまう
それぞれ説明します。
3-1:勉強の仕方が分からず、対応不十分で留年してしまう
歯学部に入学したばかりの頃、多くの学生が一つの壁にぶつかります。
それは、「勉強の仕方が分からない」という問題です。
高校までの勉強とは異なり、大学では自分自身で学習計画を立てて勉強します。
一部の学生は、勉強法がわからず留年してしまう場合もあります。
過去問をしっかり分析したり、友達と協力したりして効率よく勉強することが重要です。
3-2:専門科目が始まりテスト範囲が膨大で翻弄されて留年してしまう
歯学部の学生が特に苦労するのが、専門科目が始まる時期です。
この段階で試験範囲が急激に広がり、多くの学生がその膨大な量に圧倒されます。
一般教養科目とは違い、専門科目はその名の通り専門的な知識が求められるため、単に暗記するだけでは対応できません。
しっかり、論理を理解することも重要です。
また、専門科目は多くの場合、科目ごとに関連があります。
一つの科目でつまずくと、その他の科目にも影響を与える可能性があります。
そのため、早めに対策を講じることが、留年を防ぐ鍵となります。
3-3:4年次のCBTの範囲が膨大で留年してしまう
歯学部の4年次になると、多くの学生がCBT(Computer-Based Testing)に挑むことになります。
このテストは、歯科医師としての基礎的な知識と技術を問うもので、範囲が非常に広いのが特徴です。
そのため、多くの学生がこの試験対策に苦労します。
過去のCBT問題に取り組むことで、問題の傾向と対策を理解することが有用です。
対策問題集や塾・予備校を活用して、自分が弱いと感じる部分を強化することも効果的です。
早めの対策と計画的な学習が、4年次のCBTでの成功のかぎです。
CBTに関して詳しくはコチラの記事でも解説していますので、気になる方はぜひ一度ご覧ください。
3-4:5年次の院内実習で精神的にダメージを受け留年してしまう
歯学部の5年次になると、多くの学生が院内実習に参加します。
この実習は、実際の臨床での経験を積む重要なステップです。
多くの学生が、この期間に臨床現場についての生きた知識を学びます。
しかし、その一方で、実習は非常に厳しい環境であり、精神的にダメージを受ける学生も少なくありません。
患者さんとのコミュニケーションなどの、新たなことに挑戦するので負担に感じる人もいます。
また、実習課題を与えられ教員からフィードバックを受け課題の達成を目指しますが、そのフィードバックで厳しい指摘を受ける場合もあり、それにより精神的ダメージを受けてしまう学生もいます。
3-5:臨床実習に追われ、総合試験対策が十分にできず留年してしまう
歯学部の5年次は、臨床実習に多くの時間とエネルギーを費やす期間です。
大学によっては、5年生から6年生に進級する際に、総合試験という今まで学んだ範囲の試験が行われる場合があります。
臨床実習や課題に追われとても忙しく、範囲の広い総合試験対策を十分にできず、留年してしまう学生もいます。
そのため、時間管理が非常に重要です。
臨床実習と総合試験対策を両立させるためには、計画的に時間を使い、効率的に学習を進める必要があります。
具体的な対策としては、総合試験の範囲を早めに確認し、それに基づいて学習計画を立てることが有用です。
また、実習と試験対策を分けて考えるのではなく、お互いをリンクさせることも重要です。
実習で学んだことを総合試験の対策に活かす、逆に総合試験での学びを実習に活かすという勉強法が有効です。
3-6:6年次に難化した卒業試験で留年してしまう
歯学部の最終年度の6年次には、卒業試験が控えています。
この試験は、6年間の学習内容を総合的に評価するもので、その難易度は年々高まっています。
国家試験レベルもしくは、それ以上のレベルの問題が出題されることもあります。
また、国家試験の合格率が大学の評価に直結することもあり、合格基準が年々高くなっています。
大学によっては、多くの学生がこの試験でつまずき、留年してしまうところもあるようです。
4章:完全オンライン型「60日合格塾」のご紹介
この章では、完全オンライン型「60日合格塾」について紹介します。
- 1単元1枚のオリジナルテキスト
- アウトプット中心の個別カリキュラム
- 完全オンライン 全国対応可能
それぞれ解説していきます。
4-1:60日合格塾の特徴
「大手予備校は遠くて通うのは辛いけど、配信コースの動画講義だけでは集中力が続くか分からない」
→当塾は完全オンライン型の講義で、予備校に通う必要はありません。
動画講義だけでなくプロ講師との1対1のzoomでの講義があり、集中力を持続させます。
「個別指導塾で計画を立てて学習するのは難しそう。でも年間カリキュラムが決まっている集団講義についていけるのかは自信がない」
→あなたの学力に合ったオリジナルカリキュラムを組み、学習の進捗に応じて講師と相談の上、その都度計画を改善していきます。
また、一年間の学習計画の立て方についても無料で相談に乗ります。
「結局自分に合っているのはどの予備校なのか分からない」
→このようなお悩みでも無料で相談可能。
- 現在の成績で進級できるのか?
- 今の勉強方法であっているのか?
歯学部の進級や歯科医師国家試験に関する疑問やお悩みは、何でも相談ください。
当塾に入塾しなくても、もちろん相談費用は無料です。
もしあなたが予備校選びや勉強法に不安や迷いを感じているのであれば、ぜひ一度、当メディアを運営する「60日合格塾」に無料相談してみてください。
4-1-1:1単元1枚のオリジナルテキスト
60日合格塾では、1単元1枚のオリジナルテキストを使用したインプット方法を採用しています。
一般的な勉強法では、分厚いテキストを1ページずつ覚えていくので、知識の繋がりを意識することがどうしても難しい傾向にあります。
そこで、60日合格塾では、大きな1枚のテキストを使用して、中心となるコアな知識から枝葉を広げるように体系化して覚えていくことを推奨しています。
4-1-2:アウトプット中心の個別カリキュラム
実は、学習を進める際にはインプットだけでなく、アウトプットに重きを置いた勉強法がとても有効です。
60日合格塾では、日々の生徒自身の勉強や講師との講義の中での徹底的なアウトプットを通して、「覚えた知識を引き出す力・知識を使って考える力」を伸ばし、歯学部の進級試験や国家試験本番に対応できる力を身に付けていきます。
4-1-3:完全オンライン 全国対応可能
当塾は、面談~入塾~受講までを完全オンラインとしています。
そのため、どのような場所にお住まいでも、安心して受講することが可能です。
また、オンラインであるメリットを活かし、質問はチャットで24時間対応など、日々の学習の困りごとについてもすぐに解消できる体制を整えています。
4-2:予備校探しに迷ったら「60日合格塾」に相談を
予備校探しのお悩み、歯科医師国家試験に向けての勉強法、自分なりに学習しているが漠然とした不安がある、など「60日合格塾」になんでもご相談ください。
4–2-1:国家試験のプロが親身に相談を受けています
塾長をはじめとした受験のプロである講師やスタッフが、様々な悩みや状況に対して最適なアドバイスをさせていただきます。
年間150件以上ものご相談をいただいている対応実績もありますので、安心してご相談をお寄せください。
4-2-2:受験生だけでなく、親御様の相談も可能です
実は、「60日合格塾」に寄せられるご相談は、親御様が3割強を占めています。
面談の時間も柔軟に設定可能ですので、お仕事に忙しい親御様のご都合に合わせた対応が可能です。
もちろん、お子様本人からのお問合せ、親御様+お子様の三者面談も受け付けていますので、ぜひ相談を検討してみてください。
4–2-3:電話・メール・LINE・Zoomなど各種対応
当塾の面談の特徴は、「電話・メール・LINE・Zoom」といった各種方法に対応していることです。
もし、LINEやZoomの使い方がわからないというような場合でも、当方からお電話を差し上げることも可能です。
まとめ:歯学部は留年が多い、特徴・理由しっかり把握して対策を!
この記事では
- 歯学部での留年は多く、対策が必要であること
- 学年ごとにつまずくポイントがあり、十分な対策が必要なこと
留年している人に共通している特徴として
- 出席も試験もギリギリ狙い
- 友人が少ない
- 勉強法が独自
- 進級や留年に関心が薄い
- いつも部活の練習をしている
- 試験の制度にだけやたら詳しい
といったことがありました。
効率よく対策するには、塾の活用も有効です。
効率よく学習し、留年せずに有意義な歯学部生活を送りましょう。
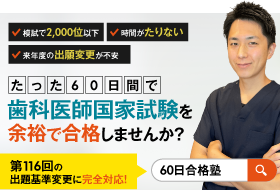
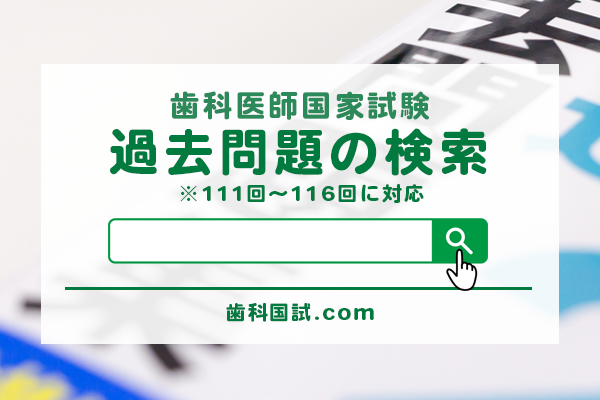


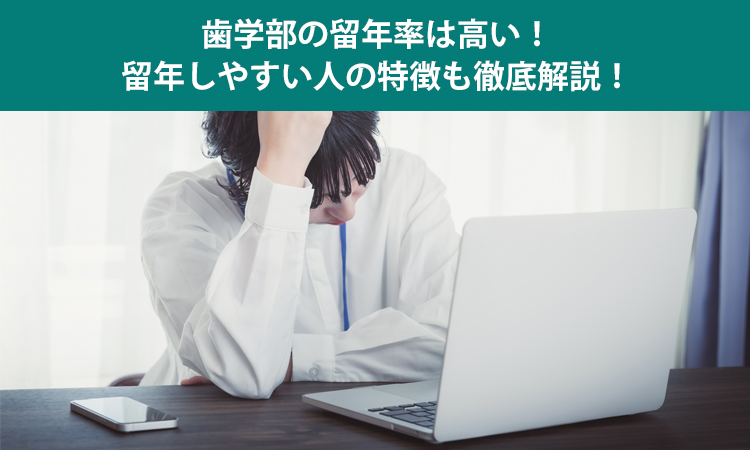
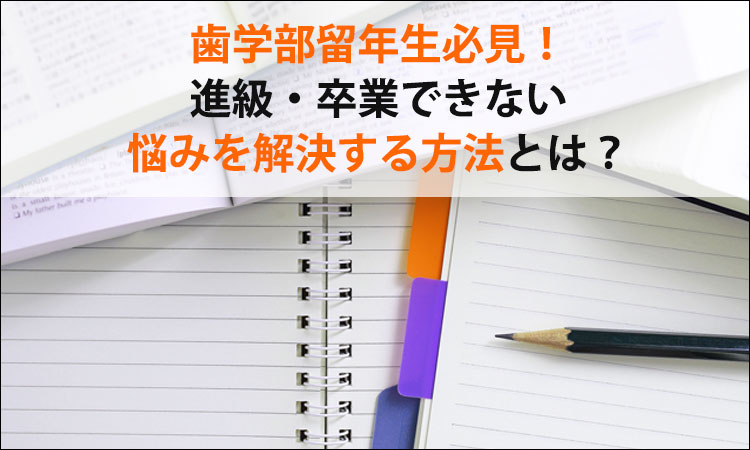
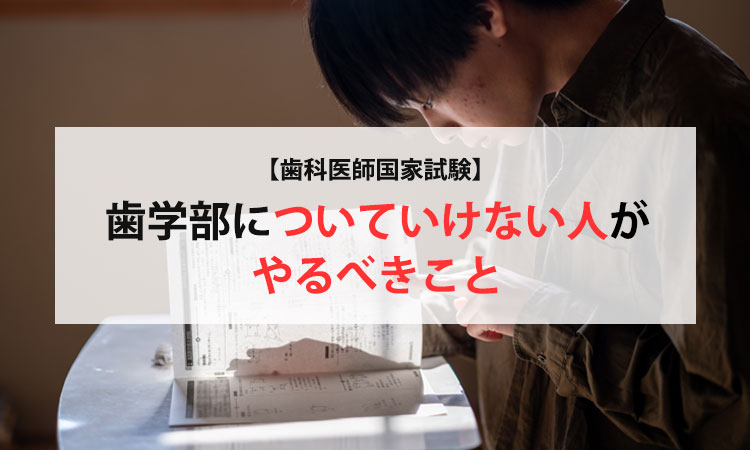

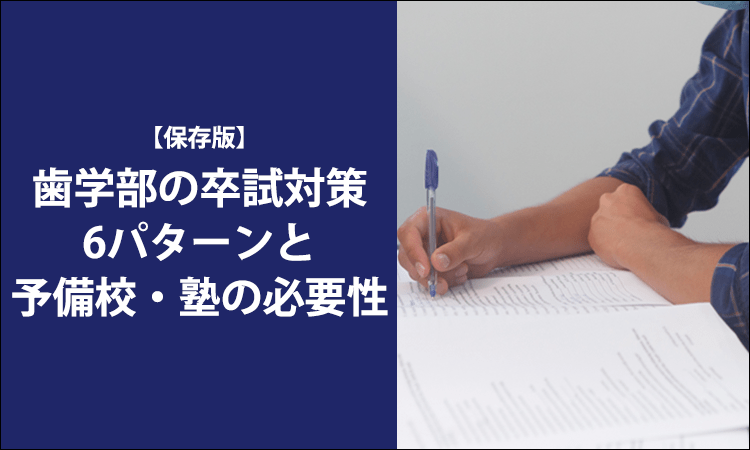



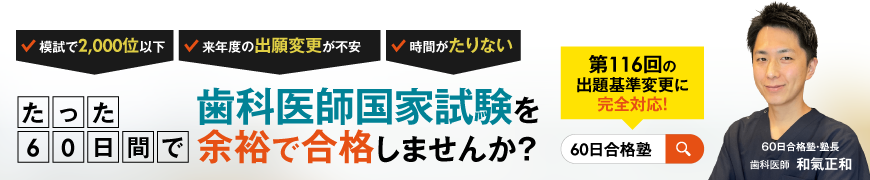
当メディア「歯科国試ドットコム」は、歯科医師国家試験の受験生が確実に合格できるように、受験生本人と親御様向けに情報提供するメディアです。
もしあなたが、歯科医師国家試験に対して不安を抱えている場合、ぜひ当メディアの記事を読んで知識やスキルを身に付け、合格に向けた正しい努力ができることを願っています。